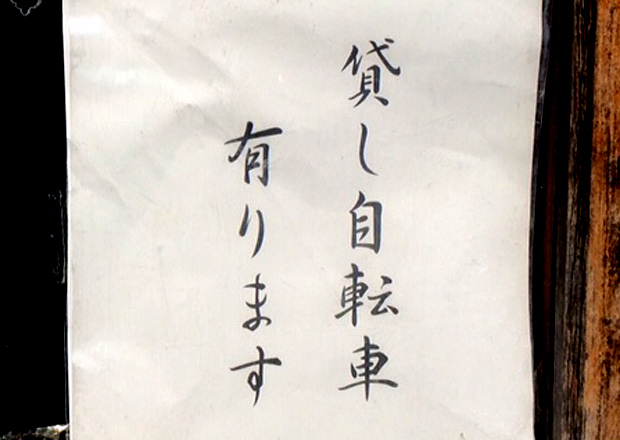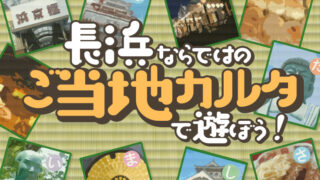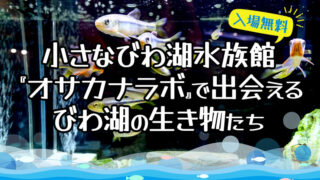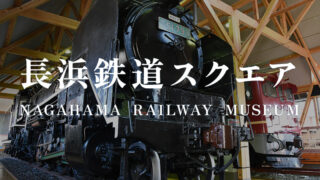友人と長浜駅前に建つ銅像の前で待ち合わせをしました。やってきた友人が突然「この人って誰?」と指をさしました。
左の人は、豊臣秀吉(羽柴)なんだけれども、右の人は誰だと思う?
JR長浜駅前にある銅像「出逢い」の人物とは?

それではここでクエスチョンです。左の人物は、豊臣秀吉公ですが、右の人物は誰でしょう?

知っていますか?

誰でしょう?

私は誰?
正解は、「石田三成公」です。(この頃は15歳で、佐吉という名前でした)
豊臣秀吉公が偉大すぎる為、どうしても影になってしまう人物ですが、長浜駅前に建つ「出逢い」の銅像は、「豊臣秀吉公と石田三成公」です。
歴史の教科書で聞いたことがありませんか?

滋賀県長浜市石田町出身、安土桃山時代の武将・大名。
天下分け目の関ヶ原の戦いで、東軍徳川家康に対し、西軍の指揮をした。歴史上評価の善し悪しが分かれる人物でもある。
いったい石田三成公は何をした人なの?
戦国武将は刀や槍を振り回して、我先にバッサバッサ敵方を倒していくイメージが強いですが、石田三成公は、どちらかというと、“食料の補給”や“馬や船の調達”、歴史の授業でも習った太閤検地(地域ごとにバラバラだった田畑の面積と収穫量の基準を全国統一し管理した)などで力を発揮しました。

現代の会社で例ると、経営や会計を考える重要な人物であり、後に天下統一を果たした秀吉公(社長)が亡くなった後も支えます。
出逢いの像は、豊臣秀吉公が石田三成公をスカウトした瞬間
織田信長公の下で、働いていた秀吉公は、姉川の戦いで大活躍をしたため、ご褒美に領地をもらいました。それがここ長浜です。

長浜に引っ越してきた秀吉公は、元々が農民の為、身内が少なく優秀な人材を探す必要がありました。
出逢いの像は、鷹狩りの最中に立ち寄った寺で、幼少の頃の三成公をスカウトする際の出来事を表現されています。この出来事を三献の茶(さんけんのちゃ)と言います。
※立ち寄った寺は、米原市の大原観音寺(おおはらかんのんじ)、古橋の法華寺の二つの説がある。
相手の気持ちを察する力が気に入られた、三献の茶の話

秀吉公が鷹狩りの最中に、近くの寺へ立ち寄った時のことです。


<一杯目> 大きな茶碗に、ぬるめの茶をたっぷり入れて出しました。


<二杯目> 先ほどより少し熱めの茶を半分ほど入れて出しました。


<三杯目> 小さな茶碗に、熱い茶を入れて出しました。


単にお茶を飲んでご機嫌になったわけではありません。相手の気持ちを察する細やかな心配りに感心した秀吉公は、三成公を雇用されたと伝わっています。

大原観音寺(米原市)に残る井戸は、石田三成が少年時代に小僧として仕えていた際、水汲みに使っていたと伝わるものです。
「出逢い」像の前で、待ち合わせるなんてオシャレじゃないか?
長浜を代表する歴史上の人物の「出逢い」を表現された銅像。長浜の玄関口にシンボルがあるだけに、ここで人と人の出逢いが生まれることを願ってつくられたものです。

歴史を知り、「出逢い」像の意味を知った今、人とこの場所で待ち合わせることが、少し特別なものに思えてきました。

「18時に渋谷のハチ公前で」なんて定番の約束にも、まったくひけをとりません。
これからも、きっと心の中でつぶやくはずです。「また『出逢い』の前で会おう」と。
秀吉・三成「出逢い」の像

| 名称 | 秀吉・三成「出逢い」の像 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県長浜市北船町2(JR長浜駅前) |
| アクセス | JR琵琶湖線「長浜駅」下車徒歩1分 北陸自動車道「長浜IC」より車で約10分 |
大原観音寺

大原観音寺は、約1200年の歴史を誇る天台宗寺院で、「三献の茶」で知られる石田三成と秀吉が運命的に出会った場所です。
その際に使われた水を汲んだという古井戸が今も残り、茶の湯伝承とともに訪れる人々を静かに迎えています。歴史好きならずとも、心を惹かれる一瞬がここにあります。
| 名称 | 大原観音寺 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県米原市朝日1342 |
| アクセス | JR琵琶湖線「長浜駅」よりバスで20分「観音寺前」下車 JR東海道線「近江長岡駅」よりバスで20分「観音寺前」下車 北陸自動車道「長浜IC」より車で約10分 北陸自動車道「長浜IC」より車で約15分 |
| 駐車場 | あり |
こちらにも石田三成公について書いています。